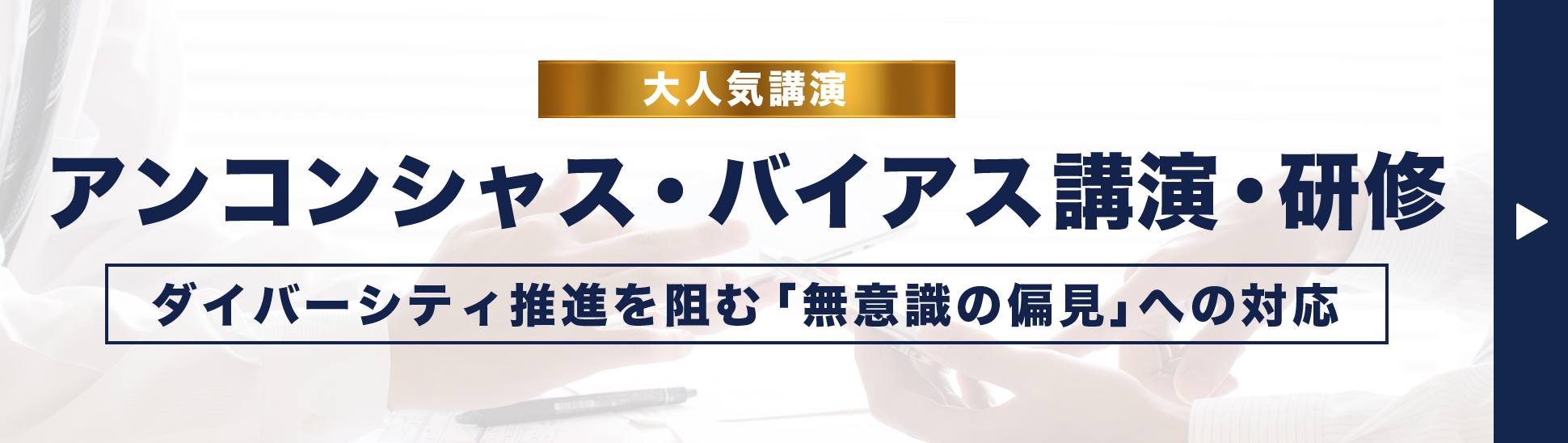アンコンシャス・バイアスとは
近年、ダイバーシディ分野において世界的に注目されているのが、アンコンシャス・バイアスです。
偏見(バイアス)とは
「偏った見方・考え方」
「客観的な根拠なしに人や集団を判断すること」
アンコンシャスバイアスとは
日本語では、無意議の偏見、アンコンシャス・バイアス、無意識バイアスと呼ばれています。
一般的に人は、自分には良識があり客観的に物事を判新できるので、「偏見(バイアス)を持っていない」と思っています。
しかし、脳科学の進展により、人間はみな偏見を持っていることがわかりました。私達はつねに瞬間的に事実やデータに基づかず、人や集団を判断します。偏見(バイアス)自体は悪くないのですが、十分な根拠なしに行うため、
正しくないことが多々あります。そのため、偏見はさまざま場面での意思決定にゆがみを与え、まちがった判断に導いてしまうのです。
アンコンシャス・バイアスの対象
偏見(バイアス)は、無意識的に、意識的にかかわらず、さまざまなところに日常的に存在します。
第一印象は大きい 見た目によってもつ強力なバイアス
私たちは人を見ると、すぐさま外見で判断します。人は見た目で決まるなどと言われるように、相手について何も知らなくても、パッと
見た感じでその人について想定し、判断し、自身も判断されるのです。
メガネをかけている = 真面目
服装が派手 = 目立ちたがり
金髪 = チャラチャラしている
高身長 = カリスマ性がある
このように、容姿、着ている服、髪の色、身長、体重、などの外見により、私たちは無意識的に相手への態度や行動を変えます。ほかにも「肩書」などの表面的な情報で判別して、
無意識的に相手との距離を調整し、態度や行動を変えることもあります。第一印象や直感を持つことは問題ないですが、意識しないと外見や表面的な情報だけで人を評価しがちになります。
事実にもとづいた情報がわかってから判断した場合とでは、人を評価したり、対応するときは、偏見への意識を高め、事実をもとにして判断に根拠を持つように心がけましょう。
血液型や出身地でも何に対してもバイアスをもつ
また、私たちは、身の回りのどんなことにもバイアスを持ちます。例えば、学歴、職業、婚姻状況、方言、 乗っている車、身長、体重、血液型や出身地、等々。「B型は自己中心的だ」、「九州人はお酒が強い」といったイメージを、自分も周囲も持っていたりします。
アンコンシャス・バイアスによってもたらされる影響
バイアス自体は悪いものではない
バイアス自体は悪いものではありません。バイアスを使わなければ、無限大の情報があふれる社会に対応できないからです。ただ、しばしば不正確な判断をしてしまうことがあります。
その歪んだ判断によって、個人と組織に及ぼされる影響を見ていきましょう。
個人に及ぼされる影響
意図しない疎外や差別に発展する人間関係の悪化
私たちは人と接するとき、知らず知らずのうちに、相手によって態度や振る舞いを変え、様々なメッセージを伝えています。
たとえ自分の感じている気持ちを言葉で言わなくても、なにげない表情や言動に表れるのです。
例1視線を合わない/言葉数が少ない/表情が乏しい/距離を置く/無視をする/軽くあしらうなどは、相手に疎外感や見下した印象を与えます。
偏見を持っている相手に対しては、言動の一つ一つは小さくても、相手が受け取るメッセージは強力なものです。
気付かないままに相手に排他的な態度や言動をとってしまうと、意図しない人間関係の悪化を招き、
差別に発展してしまう恐れがあります。
組織に及ぼされる影響
1.特定の属性が優遇される 公平性を阻害する
これまでお伝えしたように、アンコンシャス・バイアスが公平性を阻み、ダイバーシティ推進を阻害する要因であることが数多くの研究により証明されています。多様性を受け入れ、、その人のもつ能力をフルに発揮してもらうことで組織の生産性は高まります。しかし実際は。能力が同じでも、性別、年齢、国籍、人権等で評価の格差が生じています。アンコンシャス・バイアスにより、評価が歪み特定の優遇されるため、それ以外の属性の人たちが不利に扱われ、公平性が阻害されてしまうのです。そのように状態では、全メンバーが持っている能力を最大限に発揮することはできません。また、一つ一つのバイアスの影響は小さくても、それが積み重なって大きな影響を及ぼし、強い立場の人はより強く、弱い立場のひとはより弱くなっていくこともわかっています。
2.適材適所を阻む 採用・人事配置で誤った判断を下す
組織においてアンコンシャス・バイアスが最も影響を与えるのは、意思決定や人を評価するとき採用、育成、人事配置を行う場面です。

「女性には、女性ならではの仕事を与えよう」
「規模の大きな案件は男性にしかできない」
「技術者はコミュニケーション能力が低い」
「育児休業を取る男性は、昇進に興味がない」
「若い人でないとパソコン業務は勝らない」
これらの思い込みや決めつけによって能力での公平な判断ができず、適材適所がなされなくなります。そして個人の本来の能力、本質を見誤ることは、従業員の能力を十分に活用できず、人材を無駄にすることにつながり大きな損失となります。
もし十分にパフォーマンが発揮できていないチームがあったなら、アンコンシャス・バイアスの影響で適材適所になっていない可能性があります。何らかのバイアスが働いている可能性を疑ってください。
3.疎外や差別の芽になり得るハラスメントを生む

意識的なハラスメント行為も多くありますが、なかにはアンコンシャス・バイアスによって無意識のうちにハラスメントを生むこともあります。
バイアスは、思い込みや偏った考えですが、ハラスメントとは嫌がらせやいじめといった、実際に脅威を与えることを指します。
つまり、アンコンシャス・バイアスをもち、実際の行動にうつしてしまうと、それはハラスメントに発展してしまう可能性があるのです。
たとえ思い込みや考えだけで、行動にはうつさないように気を付けていたとしても、知らず知らずのうちになにげない言動として表れます。
そしてそれらが積み重なり、差別や疎外につながっていくのです。
ハラスメントの芽を摘み取るためにも、そのきっかけとなるアンコンシャス・バイアスに、企業は注意をはらわなくてはなりません。
「大阪人ってこう」がビジネスを停滞させる。無意識の偏見をグローバル企業が恐れるわけ。|ハフポストNEWS(huffingtonpost.jp)
アンコンシャスバイアスを最小限に抑えるには
「自分は何に対してもっているのか」への意識を高める
自分のキャリアや人生、組織の価値に望ましくない影響を及ぼす偏見は、排除したいものです。しかし人間である以上、帰見をもつことは避けられません。偏見があるかないかの問題でなく、「自分は何に対してもっているのか」への意識を高めることが大切です。
個人が意識を高める
1.自分が偏見を持っていると認める
まず、自分がバイアスをもっていると認めます。バイアスをもつこと自体は問題ではありません。誤った判断をし、自分や他人に対し、「不当な結果を生むこと」が良くないのです。どのような状況では偏見に委ねてよく、どのような状況ではきちんと意的に考えるべきなのかを判断するために、まず自身にも、誰にでも、バイアスがあることを認めましょう。
2.自問する 「思い込み」を疑う
まず、自分がバイアスをもっていると認めます。バイアスをもつこと自体は問題ではありません。誤った判断をし、自分や他人に対し、「不当な結果を生むこと」が良くないのです。どのような状況では偏見に要ねてよく、どのような状況ではきちんと意僕的に考えるべきなのかを判断するために、まず自身にも、誰にでも、バイアスがあることを認めましょう。
3.直感ではなく事実で 根拠をもって判断する
まず、自分がバイアスをもっていると認めます。バイアスをもつこと自体は問題ではありません。誤った判断をし、自分や他人に対し、「不当な結果を生むこと」が良くないのです。どのような状況では偏見に要ねてよく、どのような状況ではきちんと意僕的に考えるべきなのかを判断するために、まず自身にも、誰にでも、バイアスがあることを認めましょう。
「普通は」「当たり前だ」と口にしたら思い出してほしい”無意造の偏見”の存在|PHPオンライン衆知|PHP研究所
組織が意識を高める
組線がアンコンシャス・バイアスに取り組む最大の目的は、ダイバーシティ&インクルージョンを実現させるためです。誰もが機会を均等に与えられ、公平に評価され、受容される環境作りに向けて重要なのは、社員の偏見への意漬を高め、行動変革につなげることです。
1.社員教育・研修を行う「アンコンシャス・バイアス教育」の導入

まずは経営陣、マネジメント層、チーム内そして社内全体の相互理解が必要です。従案員へアンコンシャス・バイアスの存在を周知させ、教育を行いましょう。米国では棄種を問わず、あらゆる組織でアンコンシャス・バイアス教育が導入されています。弊社も企業や団体で講演、研修やワークショップを行っていますので、お問い合わせください。全従業員向けのEラーニングも提供しています。
3.履歴書から項目ごと削除する 評価者への不要な情報の排除

「オーケストラで発覚した無意識の思い込み」の事例でもわかるように、情報をインプットすることによりバイアスが生じます。評価者は、能力に関係のない情報は持たないことがベストです。
持に日本の履歴書には偏見のもととなる情報が多くあります。職務の評価に不要だと思われる項目をあげました。「写真」「氏名」「性別)「生年月日」
「住所」「連絡先」「通動時間」「扶養家族の有無」「配偶者の有無」、これらの情報は評価者には必要ありません。候補者の持つスキル、職歴、実積等、仕事に関わりのある要素だけが記載されていれば、能力だけで断することができます。
アンコンシャス・バイアスを社会全体で取り組む
幸せな社会へ近づくことへの貢献
長年かけて米国で数多くのリサーチと取り組みが行われているアンコンシャス・バイアスは、その他の国へも広まり、日本でも聞心が高まってきています。海外同様に日本でもアンコンシャス・バイアスへの理解を深め、取り組むことが不可欠な理由は、その存在と影響が社会に広く蔓延しているからです。
例えば指車的立場の女性が極端に少ない理由の一つがここに潜んでいますし、その他の社会濃題や差別、疎外、ハラスメントへつながる要因ともなっています。
日常生活でアンコンシャス・バイアスへの気づきを高め、上手に対処する行動を取り、周りの人を受容することで、誰もが気持ちよく、自分らしく働き、活躍できる社会が築かれていきます。私たち一人一人が小さな行動を積み重ねることで、より幸せな社会へ近づくことへ貴献できるのです。